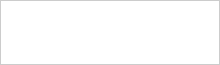根元から脚の折れてしまった椅子の修理を依頼されました。ホゾの部分だけ復元しても強度不足です。
そこで、脚一本をまるまる作って差し替えることにしました。これまでの事例紹介になかったパターンです。その過程を詳しくご覧ください。















今回、修理していて、オリジナルを改良すべき点が2点あることに気が付きました。まず脚のホゾはあくまで木目を通す方向で作られるべきで、角度をつけるなら座面の貫通孔の方にすべきです。次に背もたれの付け根はクサビで固定すべきでダボでは経年乾燥後、緩んでしまいます。この椅子は作られてから10年近く使い続けられているので、もう制作者へのフィードバックはできないことかもしれません。ですが、私が気にかかるのは、この2点に共通している考え方です。いずれもNC工作機を安易に使う都合が優先されているとしか思えないのです。手作りだったらこんな不合理なことはしないし、できないのですが、機械ならできてしまうのです。便利で強力な加工機械が使える今、専門家としての見識と知識はより厳格に適用されなければならないと思うのです。